東宝が新・帝国劇場の概要を発表 設計は小堀哲夫氏

劇場エントランス(正面より):提供元「小堀哲夫建築設計事務所」
丸の内3丁目の国際ビル・帝劇ビルを建て替える「(仮称)丸の内3-1プロジェクト」が始動した。これに伴い、ビルに入る「帝国劇場」と「出光美術館」も再整備される。帝劇ビルを所有する東宝は、新・帝国劇場の概要および設計者を発表した。発表会では、まず東宝常務執行役員エンタテインメントユニット演劇本部長の池田篤郎氏が新・帝国劇場のビジョンなどを以下のように語った。
劇場に関わるすべての人に心地良い帝劇に
東宝常務執行役員エンタテインメントユニット演劇本部長 池田篤郎氏
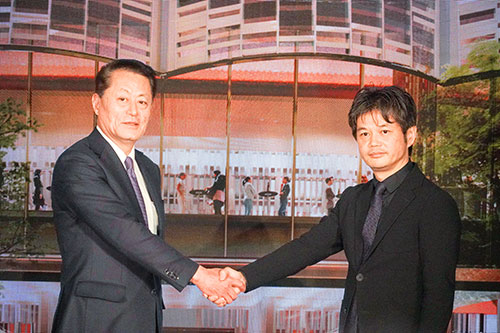
池田氏(左)と小堀氏
池田 1966年に2代目として開場したこの現・帝国劇場も、隣の国際ビルとともに再開発に入るため、2月末から休館となります。これまで多くのお客様をお迎えし、そして公演に携わったスタッフ、キャストの皆さんに、59年の長きに亘ってのご愛顧に心より御礼申し上げます。そしてこの帝国劇場でありますが、我々の先人である当社の演劇担当役員であり、希代の劇作家・演出家でもあった菊田一夫が、(建築家の)谷口吉郎先生、そして様々な皆さんと手を携えて、当時の最新技術の粋を集めてつくり上げた劇場です。そのロケーションは西には皇居の緑を望み、三方は日本のビジネスの中心である丸の内を擁し、非常に秀でた環境の中にある劇場です。
作品に関して言えば、日本初演の「風と共に去りぬ」の舞台化とミュージカル化で開場時を飾り、その後、「屋根の上のヴァイオリン弾き」「ラ・マンチャの男」などの翻訳ミュージカルで時代を刻み、そして「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「エリザベート」「モーツァルト」と、至宝の作品をつくりました。また「千と千尋の神隠し」などのオリジナル作品も数多く輩出してまいりました。
1911年、初代の帝国劇場が開場しましたが、この劇場は伊藤博文公、西園寺公望公、渋沢栄一公と、経済界の重鎮たちが日本の文化と芸術を守るために開場した劇場です。この意思を継いで2代目の劇場が立ち上がり、そして3代目となる新・劇場はこれまでの芸術性と大衆性の融合という創作の精神を受け継ぎます。これまでもそうでしたが、オーセンティック、本物であることも旨として、新しい世紀に向かって歩みを進めてまいります。
新しい劇場は見やすく、時代の要請に応えた最新技術を備え、使いやすく、お客様、スタッフ、キャスト、すなわちこの劇場に関わる全ての方々にとって心地良い帝劇であることを目指してつくります。また、劇場は街をつくります。新劇場によってこの街にまた大きな変革をもたらすことにも期待しております。
新劇場の設計者の選定は22年に指名型プロポーザル方式で行い、数多くの建築家の中からその実績、デザイン性、将来性を勘案させていただき、日本を代表する数名の建築家の皆さんにこちらから指名して提案を募り、それぞれ大変すばらしい作品を頂戴しました。そしてこの度決定した作品に関しては、帝劇の歴史とその意義に関して大変深く研究された上で、皇居、お濠端に建つこのロケーションを生かし、自然光を取り入れて四季の移ろいをビビッドに感じることができる素晴らしい提案を頂戴しました。しかもこの提案のみならず、設計者の作品にかける熱意とお人柄に関しても魅力を感じております。新・帝国劇場の設計者こそ小堀哲夫さんです。
そして、新・帝国劇場の設計者に選定された建築家で法政大学教授の小堀哲夫氏が登壇し、以下のように挨拶した。
「ヴェール」をコンセプトに様々な空間体験を実現
新・帝国劇場設計者 建築家・法政大学教授 小堀哲夫氏

池田氏と小堀氏(右)
小堀 帝国劇場に初めて訪れた時も感じましたが、時代を経ても常に色あせない感動をもっています。我が国の文化、演劇において最も重要な建築である帝国劇場の設計に携われたことを大変光栄に思っております。
新しい帝国劇場の建築デザインコンセプトであるヴェールという意味は、ヴェールがもつ言葉のもつ美しさや華やかさ、そして神秘性、これらが建築に幾重にもまとっているようなイメージになります。新しい帝国劇場におけるヴェールというコンセプトは、さらに様々な空間性を持っています。特に皇居側は美しい自然をまとったヴェールであるべきと考え、街においては帝国劇場の賑わいが滲み出るようなヴェールであるべきと考えました。また、エントランスから入った時にヴェールをくぐるように様々な空間が用意されています。エントランスから客席、舞台に続く様々な空間体験を新しい帝国劇場で実現したいと思っています。
新・帝国劇場の発表後に質疑応答があり、記者からの質問に対して東宝の池田演劇本部長と新・帝国劇場設計者の小堀氏が回答した。
――小堀氏を新・帝国劇場の設計者に選定した理由は。
池田 小堀さんの設計を見た際に、「これが帝劇だ」というのがファーストインプレッションです。歴史も研究されているし、ここのロケーションのメリットも十分体感されていて、それを生かしてくれるというのがうれしかった。我々の帝劇に対する思いがオーセンティック、本物であることに対し、小堀さんが素材の選び方も華美ではないが非常に質実伴っているものを選んでいきたいとおっしゃっている点でも信頼しています。また、平面の図面だけ見て決定されるのでなく、VRやARなどを駆使して見せていただき、本当に劇場の中にいるようなビビッドな感覚でジャッジできました。そして、小堀さんならではのスタンスで取り組まれる、小堀さんに対する信頼感、安心感をもっています。
――現帝国劇場と新・帝国劇場の違い、新・帝国劇場の特徴を教えてください。
池田 帝国劇場は日本のフラッグシップと言える劇場です。帝国劇場だからこそ上演を許可してくれたり、帝劇が世界的に認知されていたりといったことからも、それを痛感しています。この名前を引き継いでいく3代目は大きな責任を担っていくべき劇場となるので、それにふさわしい劇場となることが第一となります。
現劇場は大変モダンな建築で心地良い空間ですが、どちらかというと自然光を閉じて落ち着いた空間の劇場です。新しい劇場は小堀さんの設計で自然光を取り入れ、明るさと華やかさ、そして観劇される方が心浮き立つような空間を提供していただけると思っています。また、バリアフリー、ユニバーサルデザインに沿って設計され、全ての皆さんに心地良い帝劇を目指していくことになります。客席空間だけでなく、バックヤードや楽屋もスタッフや演者の皆さんが1日過ごすところですので、楽屋の居住性にも力を入れ、全ての人にとって心地良い空間を実現できればと考えています。
この劇場は菊田一夫という先人が心血を注いでつくり上げた劇場で、「風と共に去りぬ」を上演することが大きな目的の1つでした。地下6階地上9階の多層階を全て劇場空間に充てるというのは世界中どこにもない、誇れる劇場であると思っています。今度つくる新劇場には、舞台機構で言えば回り舞台の盆とセリはありません。今我々が上演しているものにオートメーション機構を多く使っていますが、新劇場は舞台面がフレキシブルに穴を開けることができるユニット機構になっており、奈落と連動して複雑な演出にも対応できるフレキシビリティを備えています。また、現劇場は歌舞伎のできる劇場であり幾度も上演してきましたが、花道があるが故に客席面の傾斜をそう高く持てない。新劇場はそれに制約されませんので、サイトラインを全て検証してどこからでも見やすい環境を整えることができます。客席自体も現在よりもゆとりをもたせ、かけやすい座席を考えています。
今の劇場と大きく違うところは、地下からの入口も正面エントランス同様にメインの入口として、ホワイエ的空間として、エスカレーター、エレベーターを整備するなどアクセシビリティを重視しています。また、劇場というのは観劇していただくだけでなく、劇場そのものを楽しんでいただくことが重要ですので、皆さんが利用できるカフェの空間など、街とともに劇場全体を楽しんでいただけるよう様々な工夫を凝らしていきます。バリアフリーについても、障害をもったお客様や高齢の方々が安心してご観覧できるようにその環境づくりに注力しており、正面玄関から客席に対して一直線であることが新劇場の特徴です。劇場の客席入口までフラットで段差がなく、車椅子の方でもそのまま入っていただけて、車椅子用の席も複数箇所設ける予定です。

遠景イメージ(敷地南西側より):提供元「小堀哲夫建築設計事務所」
――ヴェールをコンセプトに設計される新・帝国劇場は、改めてどのような劇場になりますか。
小堀 新しい帝国劇場は舞台の位置が90度回転することで、入口は従来と同じでも入ってから真っすぐに客席までバリアフリーでアクセスできることが、新しい特徴の1つとなります。2つ目は自然環境や周りの街との接続。特にこの場所に来て私が一番感動したのは、皇居の方からの西陽の光、水面の美しさやイチョウ並木です。そういう自然が存在している唯一無二の場所であることを皆さんにわかっていただけるようなつくり方が大事だと考えました。この街は帝国劇場と共に良くなり、そして新劇場ができることによって街と一緒に祝祭空間ができるように、エントランス側も舞台の動線に開いて、演劇を待っている人、佇んでいる人達がまるで街から舞台で見ているような、つまりここに来た人が演者として存在できるようなかたちを計画しています。街への舞台になる、その新しいフラッグシップとして、この劇場が存在していくだろうと考えています。
そして自然光をどう取り入れるかも大きなテーマにしています。劇場というのは上演になると暗い空間になりますが、徐々に暗くなっていくというそこに至るアプローチが大事で、一番外はできるだけ周りの環境がわかる空間にしたいと思っています。特に西側は人工照明や壁になっていますが、ここに関しては自然光がちょうど舞台が始まる時間から入り込んでくる、その華やかさや美しさを光の粒として取り入れながら徐々に高揚感を高めていくような空間構成にしていきたいと思っています。幾重にも徐々にシークエンスとしていろんな連続性を持つことに秀でていると思っています。
新・帝国劇場はこれまでと同様、都内の複合施設では少ない1階が客席となり、客席席数・舞台は現状と同規模としている。2月末の閉館後に解体され、2030年度に開業となる予定。
なお、三菱地所・東宝・公益財団法人出光美術館の3者で進められる「(仮称)丸の内3-1プロジェクト」は丸の内仲通り南周辺地区の都市計画手続きが開始された。三菱地所が所有する国際ビルと帝劇ビルが建て替えられ、帝国劇場と出光美術館の再整備をはじめ、皇居外苑を望む低層屋上テラスの整備、6~29階にオフィス、低層階に商業施設などが開設される。
(塚井明彦)