【連載】富裕層ビジネスの世界 24年に大きく変わる「生前贈与制度」ルールの中身
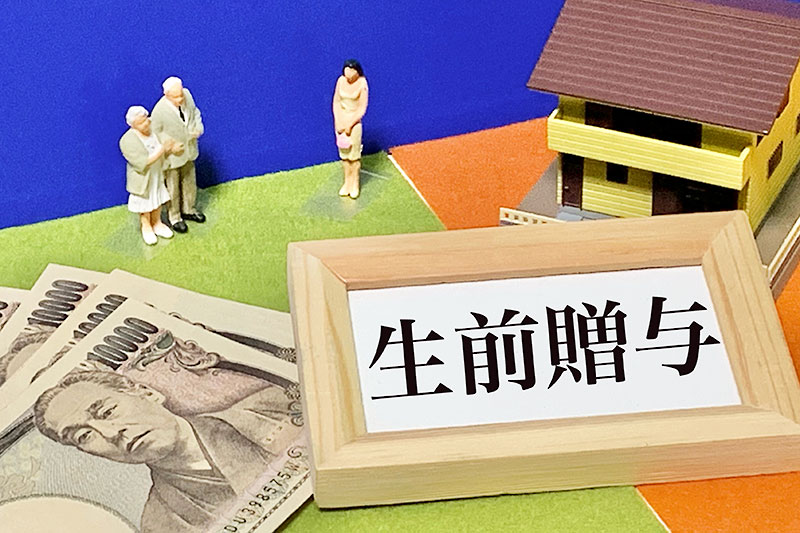
富裕層の節税の王道と言われる「生前贈与制度」が2024年1月から大きく変わる。これまで生前贈与の主流だった暦年課税贈与のメリットが縮小するのだ。
暦年課税には年110万円までは贈与税がかからない「基礎控除」がある。ただ、相続開始前3年以内の贈与については持ち戻し(=相続財産への加算)が行われている。このルールが厳しくなり、その加算期間が相続開始前7年以内へと延びるのだ。
これは、生前贈与するのなら贈与後に7年超生きないと節税メリットが得られないことを意味する。激変緩和を考慮してか、延長4年間の計100万円までは相続税非課税の措置も導入される。
逆に来年以降、使い勝手が向上するのが「相続時精算課税」だ。この制度では現状、生前の贈与は全て相続財産に加算され、相続税の節税メリットはない。少額の贈与でも申告義務があるなど使いにくさもあり、22年の課税人数は暦年課税が37.5万人なのに対し、精算課税は約4000人にとどまる。
24年1月には精算課税にも基礎控除が新設され、年110万円までの贈与であれば非課税となる。しかも、この110万円は暦年課税と違い、持ち戻しルールを適用しなくてよい。それゆえ、相続開始7年前から毎年110万円を贈与する場合、精算課税は770万円が丸ごと非課税となり、100万円しか非課税にならない暦年課税に対して圧倒的に有利となる。
精算課税制度では累計2500万円までの贈与には贈与税がかからない特別控除が引き続き設けられるが、持ち戻しにより相続税の対象となるため注意が必要だ。
国が制度の見直しに動いたのは、現状の暦年課税は資産移転の“時期に中立的でない”、すなわち期間や贈与対象者の数により税負担の差が生じているからだ。
贈与税の税率は相続税よりも高いが、財産を小分けにできる分、税負担額は抑えられる。富裕層はこれに着目し、贈与を長期間繰り返すことで、相続税の負担軽減を図っている。一方の精算課税は、資産移転の時期に中立だ。
日本の精算課税は米国を参考に03年から始まった。米国や独仏では、贈与税と相続税は統合され、贈与額と相続財産額に対し一体的に課税されている。相続税に詳しい税理士は、「精算課税の利用が暦年課税と同水準にまで増えれば、2税一体化の議論がより進むのではないか」と話す。
24年には、マンションの相続税評価額の算定に新ルールが導入され、節税メリットは減る。資産課税における公平性をどう確保するか。方向性を見極める上で大事な年になる。